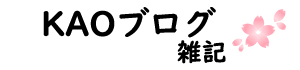アパートでの騒音の許容範囲は、時間帯や場所によって異なります。
でも、「騒音」と判断する基準って、明確な答えがないのが現状です。
そうなってしまう理由は、
などが、複雑に絡んでいるためです。
最近は在宅勤務や夜勤など、様々な生活スタイルの人が増えているため、より近所トラブルが起きやすくなっています。
しかし、明確な基準はなくても、”線引きの目安”というのは存在します。
この記事では、
が分かるよう、音の関する「一般的な許容範囲」について紹介していきます。
アパートの騒音、どこまでが「普通」?
こうした疑問や不安を感じる人は、とても多いです。
実際、“騒音かどうか”の判断はとても曖昧で、感覚に頼りがちです。
一般的な生活音の目安(dB)
音の大きさは「デシベル(dB)」という単位で、客観的判断が可能です。
以下は、代表的な生活音の目安になります。
| 音の種類 | dBの目安 | 解説 |
|---|---|---|
| ささやき声 | 約30dB | 非常に静か。深夜でも問題になりにくい。 |
| 普通の会話 | 約50〜60dB | 隣室との壁が薄いと聞こえることがある。 |
| テレビ(普通の音量) | 約60dB | 昼間は許容範囲、深夜は注意が必要。 |
| 足音(歩行) | 約40〜60dB | 木造アパートでは響きやすい。 |
| 掃除機・洗濯機 | 約60〜70dB | 使用する時間帯に配慮が必要。 |
特にアパートなどの集合住宅では、時間帯と頻度によって「許容範囲かどうか」が大きく変わります。
音の感じ方は人それぞれ
このように数値である程度の目安はあるものの、一日を通して計測するわけではなく、しかも騒音の感じ方には個人差があります。
たとえば、60dB程度の音(普通の会話)でも「うるさい」と感じる人もいれば、気にならない人もいます。
これは、過去の経験や体質(聴覚過敏など)、ストレス状態によって左右される「主観的な感覚」です。
一方で、騒音計などで数値化できる音の大きさや、時間帯別に定められた行政の騒音基準など、客観的な基準も存在します。
苦情を考える前に、「音が客観的にどの程度のレベルか」を知ることが大切です。
【アパートの騒音】一般的な許容範囲とは?

騒音基準(dB)から判断
では、どのくらいの音からが騒音となるのでしょう?
| 昼間 | 夜間 | |
|---|---|---|
| 基準(dB) | 55以下 | 45以下 |
1日の中で、何回か基準を超えてるくらいでは、”騒音”と言い切るには弱いです。
しかし、
と明らかな場合、「騒音」となる可能性が高くなります。
騒音の数値をもっと正確に計ってみたい場合は、騒音計本体での測定が確実です。
安い機械で、1,000~2,000円で販売されていますよ。

興味がある方は、ぜひ。
\こんな記事もcheck/
木造アパートはやめたほうがいい?音がとにかく響く!特に注意してほしい人
騒音の時間区分
騒音の観点でみたときに、時間区分の捉え方は諸説あります。
ですが一般的な昼間と夜間は、以下のようになっています。
| 昼間 | 夜間 |
|---|---|
| AM6:00~PM10:00 | PM10:00~AM6:00 |
細かく分ければ、「早朝」や「深夜」の区分もあります。
しかし、”何時から何時まで”のように、はっきりとした定義はありません
ちなみに、選挙カーによる演説は「午前8時から午後8時まで」。

このことから、20:00~8:00はできるだけ大きい音を出さないというのがマナーと言えそうです。
個人的には、
といった解釈が妥当かと思います。
特にアパートなどの防音性の低い集合住宅ですと、より気をつける必要があるでしょう。
環境からみた許容範囲

建物の構造による聞こえ方の違い
建物の構造も意外と見落とされがちです。
造りで防音性が大きく違いますし、周囲への響き方も異なります。
集合住宅だと防音性が低い順から、
となっています。
つまり、同じ音を出したとしても、建築構造によって聞こえ方が異なるのです。
そのため、防音性が低い物件ほど生活音の許容範囲が狭くなります。

だからといって、「木造だからここまで」「鉄筋であれば許される」というわけではありませんけどね…。
このことから、建物の構造によっても許容範囲が変わると言えるのです。
周辺環境による違い
騒音は、周辺環境にも左右されます。
例えば、
といった場合です。
このように周囲が賑やかだと、建物内の生活音がまぎれやすくなります。
それに対して。
閑静な住宅街だと音が響きやすく、周囲の生活音が感じやすくなります。
よって建物の構造だけでなく、周辺環境でも変わるのです。
子供がいる場合の騒音基準
子供が騒音源の場合は、「ある程度は仕方ない」と捉えられるのが一般的です。
でも逆に、「子供だから仕方ない」も、簡単に通用するわけでもありません。
それは、今まで述べてきたような判断材料があるためです。
子供の騒音だったとしても、
といった内容に当てはまれば、十分「騒音」と判断されることもあります。
よく、「受忍限度を超えている」と表現されますね。
いわゆる裁判になった場合、不利になります。
侵害の程度が著しいと、このように判断されます。
でもやはり、音を出してるのは「子供」なわけですし…。
「親の常識的、かつ誠意のある対応があるかどうか」も、1つの判断ポイントになるようです。
管理会社等の相談で見えてくることも

管理会社に相談という形で問い合わせてみる
もし、騒音に悩んで、
という場合。
管理会社に「苦情」ではなく、「相談」という形で問い合わせてみるのもひとつの手です。
でもOKです。
「これは生活音の範囲カモ!?」
って思っていても、意外にも相談したら、
「それはちょっと迷惑ですね~。対応します」
なんて言われることもあります。
他の住人がヒントになる!?
そして管理会社に相談したことで、見えてくることもあります。
例えば、
など、他の住人がヒントになることもあるのです。
やはり、周辺環境や建築構造によっても大きな違いがあるため、同じ物件に住む他の住人の意見や苦情は、参考になります。
すると自分の中で、
といった共感をもつことができ、不思議と騒音があまり気にならなくなったりといった思わぬ効果も生まれたりします。
この記事のまとめ
今回の内容を頭に入れておくと、騒音の被害を受けている場合は、苦情を言う際の判断材料になるのではないかと思います。
たとえ生活音でも、程度が著しかったり頻度が多ければ立派な騒音です。

生活音ではなく、生活騒音です。
騒音の被害を受けていてどこまで我慢すべきか迷う場合は、許容範囲についてある程度理解し、今後の役に立ててください!