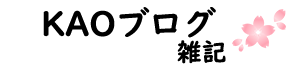アパートでの騒音の許容範囲は、時間帯や場所によって異なります。
でも、「騒音」と判断する基準って、明確な答えがないのが現状です。
そうなってしまう理由は、
などが、複雑に絡んでいるためです。
最近は在宅勤務や夜勤など、様々な生活スタイルの人が増えているため、より近所トラブルが起きやすくなっています。
しかし、明確な基準はなくても、”線引きの目安”というのは存在します。
この記事では、
が分かるよう、音の関する「一般的な許容範囲」について紹介していきます。
【アパートの騒音】一般的な許容範囲とは?

騒音基準(dB)から判断
まず、騒音を判断するひとつの指標として、デシベル(dB)があります。
以下は、アパート(住宅地)での基準になります。
| 昼間 | 夜間 | |
|---|---|---|
| 基準(dB) | 55以下 | 45以下 |
1日の中で、何回か基準を超えてるくらいでは、”騒音”にはなりません。
でも、
と明らかな場合、「騒音」となる可能性が高くなります。
試しに計測してみたい場合、スマホアプリで「騒音計」と検索してみてください。
簡易的ではありますが、周囲の音(dB)がどのくらい出ているのか把握できます。
「騒音の数値をもっと正確に計ってみたい」という方は、騒音計本体での測定が確実です。
安い機械で、1,000~2,000円で販売されていますよ。

興味がある方は、ぜひ。
\こんな記事もcheck/
木造アパートはやめたほうがいい?音がとにかく響く!特に注意してほしい人
騒音の時間区分

騒音の観点でみたときに、時間区分の捉え方は諸説あります。
ですが一般的な昼間と夜間は、以下のようになっています。
| 昼間 | 夜間 |
|---|---|
| AM6:00~PM10:00 | PM10:00~AM6:00 |
細かく分ければ、「早朝」や「深夜」の区分もあります。
しかし、”何時から何時まで”のように、はっきりとした定義はありません
ちなみに、選挙カーによる演説は「午前8時から午後8時まで」。

このことから、20:00~8:00はできるだけ大きい音を出さないというのがマナーと言えそうです。
個人的には、
といった解釈が妥当かと思います。
特にアパートなどの防音性の低い集合住宅ですと、より気をつける必要があるでしょう。
環境からみた許容範囲

建物の構造による聞こえ方の違い
建物の構造も意外と見落とされがちです。
造りで防音性が大きく違いますし、周囲への響き方も異なります。
集合住宅だと防音性が低い順から、
となっています。
つまり、同じ音を出したとしても、建築構造によって聞こえ方が異なるのです。
そのため、防音性が低い物件ほど生活音の許容範囲が狭くなります。

だからといって、「木造だからここまで」「鉄筋であれば許される」というわけではありませんけどね…。
このことから、建物の構造によっても許容範囲が変わると言えるのです。
周辺環境による違い
騒音は、周辺環境にも左右されます。
例えば、
といった場合です。
このように周囲が賑やかだと、建物内の生活音がまぎれやすくなります。
それに対して。
閑静な住宅街だと音が響きやすく、周囲の生活音が感じやすくなります。
よって建物の構造だけでなく、周辺環境でも変わるのです。
子供がいる場合の騒音基準

子供が騒音源の場合は、「ある程度は仕方ない」と捉えられるのが一般的です。
でも逆に、「子供だから仕方ない」も、簡単に通用するわけでもありません。
それは、今まで述べてきたような判断材料があるためです。
子供の騒音だったとしても、
といった内容に当てはまれば、十分「騒音」と判断されることもあります。
よく、「受忍限度を超えている」と表現されますね。
いわゆる裁判になった場合、不利になります。
侵害の程度が著しいと、このように判断されます。
でもやはり、音を出してるのは「子供」なわけですし…。
「親の常識的、かつ誠意のある対応があるかどうか」も、1つの判断ポイントになるようです。
この記事のまとめ
今回の内容を頭に入れておくと、騒音の被害を受けている場合は、苦情を言う際の判断材料になるのではないかと思います。
たとえ生活音でも、程度が著しかったり頻度が多ければ立派な騒音です。

生活音ではなく、生活騒音です。
だからといって、ひそひそと過ごすことはありませんが、集合住宅の場合は最低限のマナーは守る必要があります。
騒音の被害を受けている場合は、許容範囲についてある程度理解し、今後の役に立ててください!