集合住宅での防音対策。
子供がいる家庭は、より慎重になりますよね!?
そう思って対策したのに…!
いざ取り入れてみても、「普通に苦情がきた」というパターン、珍しくありません。
子どもの足音が気になって、口コミの良い防音マットを買ってみても、正直…。
期待していたほどの効果はなかったりします。
でも、いろいろ試してみるうちに「なぜ効かないのか」「どんな対策なら意味があるのか」が少しずつ分かってきました。
この記事では、
を、リアルな体験談を交えて紹介します。
【賃貸】防音マットの効果が限定的な理由
「防音マット」って聞くと、“音をシャットアウトしてくれる”イメージ…。
でも、残念なことに…。
実際は、防げる音の種類が限られているのです。
防ぐのは“軽い衝撃音”だけ

防音マットが得意なのは、たとえばこんな音です。
こういった“軽い衝撃音”には、マットがクッションの役割をしてくれるので、ある程度効果があります。
特に厚みがあるタイプなら、床に直接響く音をやわらげてくれます。

でも──ここが大事なポイントです。
“振動音”や“構造伝達音”には効果が薄い
子どもの「ドスドス」という足音。
大人みたいに体重が重くないし、一見、そんなに響いていないような気がしますが…。
結構、強烈に響いています。
これらは、床全体や建物の構造を通して伝わる””振動音””です。
つまり、床の上にどんなにマットを敷いても、音のもとが床を通して伝わっているので、防ぎきれません。
とくに、木造や軽量鉄骨のアパートでは、床の構造が薄く振動を吸収しにくいため、効果を感じにくいのです。
賃貸で特に効果が出にくい理由
そして、防音マットの限界をさらに感じやすいのが、「賃貸住宅」。
その理由は、大きく3つあります。
- 床の下地が薄い(クッション材がほぼ無い)
→ 音や振動がそのまま下の階に伝わりやすい。 - 防音リフォームができない
→ 床下に防振材を入れたり、床を張り替えたりできないため、根本的な対策が難しい。 - 構造的に音が響きやすい
→ 特に木造や軽量鉄骨では、振動音が壁や柱を伝って部屋全体に響きやすい。
つまり、マットの性能だけではなく建物構造そのものが原因なのです。
実際に試した結果・体験談
では!
私が実際に試したマット、効果があった音の種類などについてです。
どんなマットを使ったか
実際に、
- ラグマット
- ジョイントマット
- プレイマット
を使用したことがあります。
正直なところ、全て意味なし、あるいは軽減程度といったところ…。

これが現実です。
あとは、音を受ける側の許容範囲次第でしょう。
効果があった/なかった音の種類
では次に、効果があった/なかった音の種類についてです。
▼効果があった音の種類
▼効果がなかった音の種類
つまり、
子供がよほどゆっくり歩かない限り、
””全ての足音(小走り、走りまわる、ジャンプ、地団太など)””
が響いている
と言えます。
家族構成・部屋環境(子どもの足音など)
うちは、3歳の女の子一人です。
賃貸マンション住まいで、
そんなに活発な方ではないですが、
といった行動が響いてしまっているようです。
もちろん、何も対策していない床はもってのほかですが…。
ジョイントマットを引いてる上でも普通に聞こえてしまう(特に下階に)のが、現実です。
子供が2人以上や、男の子など活発な子だと当然音が出る頻度やボリュームも増すので、より徹底した防音対策が必要になります。
より効果的だった対策は?

では!!
より、防音効果を高めるためのアドバイスをしていきます!
プレイマットが一番効果あり!?
プレイマットの効果
いろいろな防音マットを試してみましたが…。
最終的に一番「効果ある!」と感じたのは、子ども用の””プレイマット””。
実際に敷いてみると、床に響く音がかなりやわらぎます。
賃貸住まいである以上、やはり完全な防音対策はないので…。
多くの「防音対策商品」の中でも、特に優れた”プレイマット”を取り入れることで、最大限の対策になると言えるでしょう。
厚みがあって、しっかり衝撃を吸収してくれる
一般的な防音マットは、1cm前後がほとんど。
それに対し、プレイマットは2〜4cmほどの厚手タイプが多く、クッション性が段違いです。
子どもが座るときの「ドスン」や、おもちゃを落としたときの「コトン」という音が、かなりマイルドになります。
素材が柔らかく、音の“跳ね返り”が少ない
防音マットは素材が硬めで、軽い衝撃音なら防げても、“ドンッ”という強い音は床に伝わりやすくなります。
その点プレイマットは、沈み込むような柔らかさがあるので、衝撃を吸収してくれる感覚がしっかりあります。
物件選び時に確認すべき構造ポイント
防音マットやプレイマットで、ある程度音を和らげることはできますが…。
やはり、建物そのものの構造がそもそもの原因です。
だからこそ、賃貸物件を選ぶときには、最初に確認しておくべきポイントがあります。
床の厚み・下地の種類をチェック

厚みがある床やしっかりした下地がある物件ほど、生活音が響きにくいです。
階数・上下の部屋の状況を確認
壁や天井の厚み・素材も意外と重要
基本的に、
【マンション】
RC造(鉄筋コンクリート)
か
SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート)
と言えます。
そのため、少しでも防音効果を高めたいのであれば、”マンション”に絞って物件を探すとよいです。
物件の間取り・家具の置き方もポイント
こういった「間取り」もポイントになるので、防音対策がしやすいお部屋選びも大切です!
防音マットよりも最強と言える方法とは?
「防音マット」について、いろいろと触れましたが…。
でもやっぱり、一番効果的なのは、
周囲の住人の仲良くなること
これに尽きます。
防音マットで完全に防げないなら、心理的なアプローチが非常に効果的です。
普段から、
といったことを心がけると、防音対策以上の効果を発揮するのです。
まとめ
防音マットは部分的な対策としては有効
今回紹介したように、防音マットは万能ではありません。
特に、木造や軽量鉄骨の賃貸では、振動音や走る音などを完全に消すことは難しいからです。
構造が一番強い賃貸マンションだったとしても、やはり完全に音を消すことは不可能と言えます。
でも、軽い衝撃音やおもちゃの音をやわらげるといった部分的な効果は十分にあります。
つまり、防音マットやプレイマットは、あくまで「補助的な対策」として活用するのが現実的です。
目的に合わせて対策を組み合わせよう
大切なのは、自分の目的に合わせて複数の対策を組み合わせること。
こうした工夫を組み合わせることで、賃貸でも思った以上に騒音を抑えられます。
防音マットだけに頼らず、いろいろな対策をうまく組み合わせることが、快適な暮らしへの近道になります♪
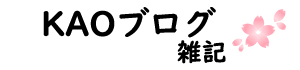









コメント